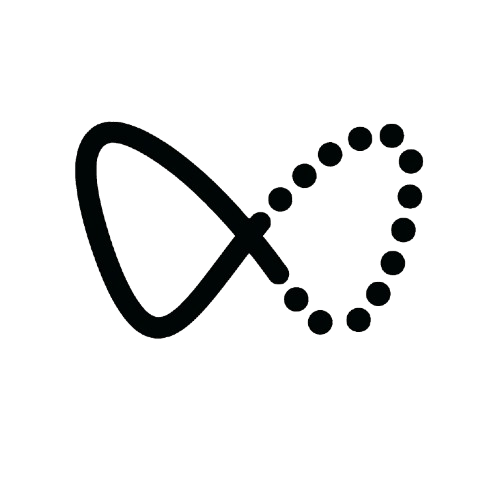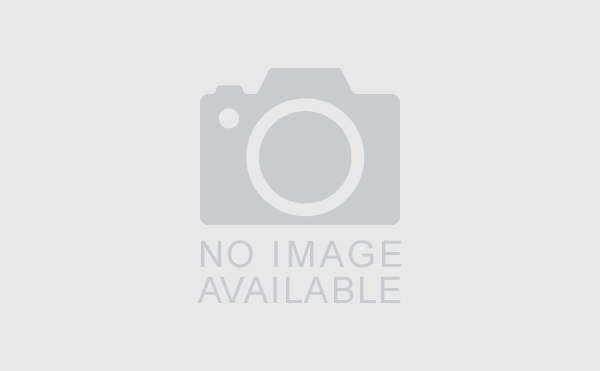行動できない理由は思考の渋滞かもしれない―心理学と実行デザインで読み解く「動けなさ」の正体―
動けない日は、誰にでもある
やる気はあるのに、なぜか手が動かない。時間もあるのに、いつの間にか一日が終わっていた。そんな日が続くと、自分を責めたくなるものです。
でも、それは意志が弱いからではありません。止まっているのは「あなた」ではなく、「流れ」そのものかもしれません。
情報も感情も飽和すると、脳は静かになる
現代は、情報も感情も刺激も多すぎる時代です。目に入るもの、考えること、決断しなければならないこと……。
こうしたすべてが同時に脳内に滞留すると、やがて処理が追いつかなくなります。これは心理学で「認知過負荷(cognitive overload)」と呼ばれています。
わたしたちの脳は、自分を守るために「判断の保留」という選択をとります。つまり、行動を止めるという形で、静かに自分を守っているのです。
自分を責める前に、問いを変えてみる
行動できなかったとき、「どうして何もできなかったんだろう」と問いがちです。
でもその前に、「いま、何が詰まっていたんだろう」と尋ねてみてください。
古代ローマの哲人マルクス・アウレリウスは、自省録の中でこう記しています。
苦しみは、出来事そのものからではなく、それをどう解釈するかによって生まれる。
わたしたちは、動けないことよりも、「動けない自分」にラベルを貼ることで苦しみを深めてしまっていることがあるのです。
停滞の裏側にある静かなプロセス
迷いや躊躇が続くとき、それは内側で何かを組み立てている時間かもしれません。
ゴッホが『夜のカフェテラス』を描いたのは、精神的に不安定な日々の中でした。筆が止まるような日々も、絵の中には色として静かに流れていたのかもしれません。
内側で育っている何かは、表に出るまでに時間がかかることがあります。
小さく動き出すための3つの工夫
- 今日はやらないことを決める
余白をつくることで、何を本当にやりたいかが見えやすくなります。 - 問いをそのまま書き出す
正解を出さなくていい。ただ、今心にある問いを紙に書くだけでも脳の渋滞が和らぎます。 - タスクを「1歩以下」に分解する
たとえば「資料を作る」は、「ファイルを開く」くらいまで小さくする。デカルトも「複雑な問題は細かく分解せよ」と語りました。
迷っているときほど、思考は動いている
行動できないと感じる時間も、実は内側ではたくさんのことが動いています。
見えないところで芽が出る準備をしているように、迷いや止まりの感覚も、流れの一部かもしれません。
そして、そのことに気づいているあなたは、すでに流れの中にいるとも言えます。
参考文献
- American Psychological Association (2020). Cognitive Overload and Decision-Making
- Zeigarnik, B. (1927). On finished and unfinished tasks
- Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond
- Marcus Aurelius. Meditations
- René Descartes. Discourse on the Method
- Vincent van Gogh, Café Terrace at Night (1888)
関連サポートのご案内
思考と行動のあいだに、やさしい流れをつくるサポートを行っています。
無料でのご相談も承っています。お気軽にご活用ください。