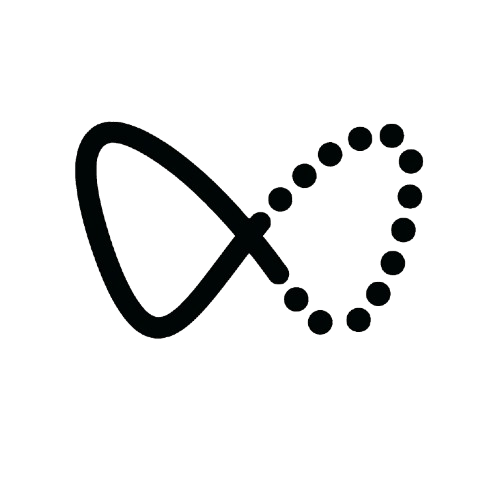心理的安全をつくるのはルールではなく“予測可能性”だった

「心理的安全=仲良し」ではない
心理的安全という言葉が広まりましたが、誤解も多くあります。
よくある誤解が「何でも言える関係=心理的安全」だというもの。しかし、本質は“自由”ではなく“予測可能性”にあります。
本記事では、心理的安全の本質を構造と脳科学の視点からひもときます。
そもそも「心理的安全」とは?
この概念を世界的に広めたのは、ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン。
彼女は『チームが機能するとはどういうことか』の中で、心理的安全を次のように定義しています:
「このチームでは、ミスをしても罰せられないと信じられる状態」 「自分らしさを出しても否定されないと信じられる状態」
つまり、心理的安全とは“罰されるかもしれない”という無意識のブレーキが外れた状態なのです。
ルールでは「安全」は担保できない
多くの組織が「心理的安全をつくるためにルールを定めよう」とします。
- 否定しない
- 話を最後まで聞く
- 受け入れ合う文化をつくる
しかし、ルールがあっても、それが実際に守られるかどうか分からないなら、人は安心できません。
むしろ、明文化されたルールほど、破られたときの「裏切られ感」が大きくなるのです。
人が安心を感じるのは、「予測できるとき」
『心理的安全性のつくりかた』(石井遼介)では、心理的安全を「予測可能性の精度の高さ」と定義しています。
つまり、人はこう思っています:
「この人と話したら、たぶんこう返してくるだろう」
「この話題でも、たぶんジャッジされないはずだ」
この“たぶん”の精度が高いほど、人は安心し、自由に発言したり行動したりできるのです。
脳科学から見る「予測」の重要性
脳は常に「次に何が起きるか」を予測しています。予測と現実のズレが小さいほど、安心を感じます。
これは神経科学における「予測処理理論(Predictive Coding)」にもとづく考え方で、脳は差分(エラー)を最小化するように働いているのです。
つまり、安心とは予測通りであることであり、ルールではなく「行動の一貫性」から生まれるのです。
行動の一貫性が「安全」をつくる
たとえば次のようなふるまいが、心理的安全を生みます:
- ミスしたときも変わらぬ態度で接する
- 意見の食い違いがあっても、遮らず聞く
- 否定されそうな発言にも、感情的にならず向き合う
これらは全て、相手に「予測可能なふるまい」を積み重ねていく行為です。
「意見の言いやすさ」ではなく「反応の読みやすさ」
心理的安全な場をつくるには、「意見を言える自由」を与えるよりも、反応に一貫性を持たせる方が重要です。
なぜなら、人は発言の自由があっても、「どう返されるか分からない」なら発言しないからです。
つまり、リーダーやファシリテーターが意識すべきは“反応の予測可能性”なのです。
「関係性の安全設計」が鍵になる
心理的安全は「人柄」ではなく、「関係の設計」でつくられます。
それは以下のような要素を意図的にデザインすること:
- 定例性:接点を定期的に持つ
- 共有フレーム:判断基準・ゴールを共に持つ
- トーンの一貫性:感情や言葉のトーンを安定させる
これらの積み重ねが、ルールよりも深い安心をつくります。
まとめ:「予測可能性=信頼のインフラ」
心理的安全とは、ルールでも雰囲気でもなく、予測可能性の設計によって生まれる構造です。
関係性の中で「裏切られない」「変わらない」という経験が蓄積されることで、人は安心し、本音・挑戦・協働が生まれます。
だからこそ、リーダーや場をつくる人が担うべきは、「一貫した反応」という構造の提供なのです。
関連書籍のご紹介
- 『チームが機能するとはどういうことか』エイミー・C・エドモンドソン
- 『心理的安全性のつくりかた』石井遼介
- 『予測する脳』安西祐一郎(予測処理理論の入門)
関連サービスのご案内
「信頼されるふるまい方」や「関係性の構造設計」を実践したい方へ。
Mebukiの1on1セッションでは、対話と構造の両面からあなたの在り方を整えます。
- 心の知性DQとEQを徹底解剖 — 品位が人と組織を根底から変える理由

- 知性は心にも宿る — DQとEQがチームと組織に与える本当の影響

- “従順”と“協調性”は違う — 自立したチームをつくる思考と対話のスキル

- ちゃんと話してるのに、噛み合わない理由 — 対話には“見えない設計”がある

- 感情に流される人と、感情を「材料」にする人の違い

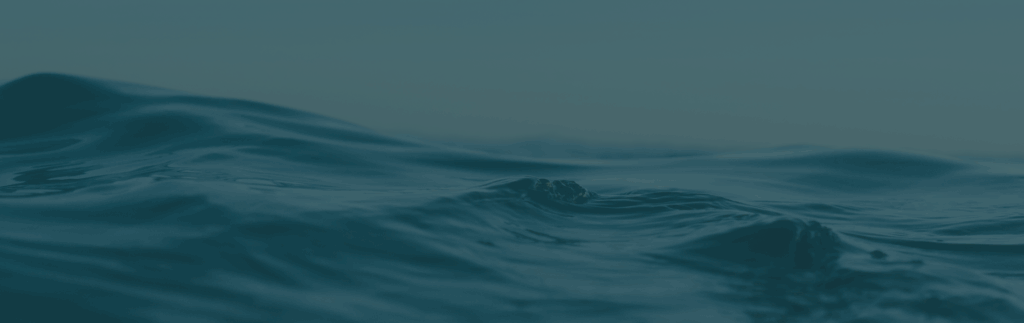
まずは、無料カウンセリングにお越しください。
所要時間:30分(Zoom)事前ヒアリングなし
話したいことがあるだけでOK。
無理な営業・勧誘はありません。あなたの「今」を聞かせてください。