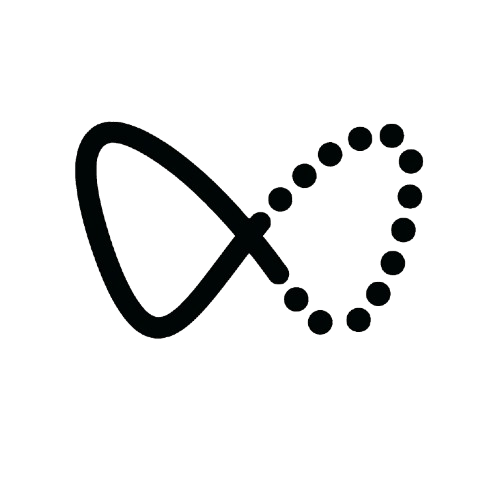感情的に動くチームと、感情を設計するチームの差とは何か

はじめに:「雰囲気」で動くチームの危うさ
会議で話が迷走する、誰かの機嫌に左右される、メンバー間の不信感が空気に滲む。
チームで働く中で、「感情のゆらぎ」が成果に影響する場面は少なくありません。
それは“人間だから仕方ない”ことでもありますが、
放置すればチームのパフォーマンスは偶然性に委ねられます。
本記事では、「感情に振り回されるチーム」と「感情を設計するチーム」の構造的な違いを明らかにし、
安定した意思決定と信頼形成のための設計の視点をお伝えします。
感情はチームの“不可視インフラ”である
感情は目に見えないけれど、確実にパフォーマンスに影響する“情報空間”です。
組織心理学者マーク・ブラヴォは、
「チームの成果は、タスク設計だけでなく“感情の処理力”に左右される」と述べています。
よくある問題:
- 感情を「個人のもの」として処理し、構造に取り込まない
- その場のノリ・テンションで動きが決まってしまう
- 指摘が感情論と受け取られ、議論が止まる
感情はマネジメントできないものではありません。
“扱い方を知らない”だけで、感情設計は十分に可能です。
違い1:判断の基準が“気分”ではなく“仕組み”にある
感情的に動くチームは、「そのときの空気」で方向性が変わります。
一方、感情を設計するチームは、判断の基準を仕組みで定義しています。
経営学者ピーター・ドラッカーは「感情を排除するのではなく、判断を構造化せよ」と提言しています。
推奨アクション:
- 判断基準や評価軸をあらかじめ言語化しておく
- 「これは誰のどの責任領域か」を明確にしておく
- 意見が出る前に「話す順番・優先事項」を合意する
感情の揺れを“個人の問題”にせず、「構造の誤差」として見直す視点が重要です。
違い2:感情の“ログ”と“フィードバック”が存在する
感情的なチームでは、違和感やモヤモヤが蓄積しやすく、
爆発するまで顕在化しません。
対して、感情を設計するチームでは、感情の小さな変化を言語化する習慣が存在します。
推奨アクション:
- 会議の冒頭に「状態シェア(1分)」を設ける
- チェックイン・チェックアウトで“気分”も確認する
- 定期的に「感情のフィードバックタイム」を設ける
感情を扱うのは難しそうに見えますが、
一定のルールと場があれば“情報”として取り扱えるようになります。
違い3:「不機嫌の力学」を見える化している
チーム内で、誰かの不機嫌や焦りが連鎖して雰囲気を支配する。
これを“なんとなく我慢”でやりすごすと、知らぬ間に心理的安全性が損なわれます。
スタンフォード大の心理学者ジェニファー・アーカーは、
「感情は“伝染”するものであり、リーダーの感情はチーム全体に波及する」と指摘しました。
推奨アクション:
- 定期的に「感情の起点」になっている人の影響力を観察する
- 不機嫌の背景にある“構造上のズレ”を言語化する
- 不調のときに「支えられる仕組み」があるかを点検する
感情設計の鍵は、個人ではなく“チームの構造”に注目することです。
まとめ:感情は「消す」より「扱える」ことが価値になる
感情のあるチームであること自体は、むしろ健全です。
重要なのは、それを扱える“構造”と“習慣”をチームとして持てるかどうか。
感情的なチームは、感情に引っ張られて動く。
感情を設計するチームは、感情を“使いながら”動く。
両者の違いは、結果だけでなく、信頼の総量と継続性に現れます。
mypmでは、チームの感情構造と行動設計を支援しています
mypmでは、感情ログ・振り返り習慣・評価軸の設計などを通じて、
“チームで動くための感情設計”を伴走サポートしています。
成果も人間関係も両立させたいチーム・リーダーの方へ。
まずは無料のカウンセリングで、構造から見直してみませんか?
- 心の知性DQとEQを徹底解剖 — 品位が人と組織を根底から変える理由

- 知性は心にも宿る — DQとEQがチームと組織に与える本当の影響

- “従順”と“協調性”は違う — 自立したチームをつくる思考と対話のスキル

- ちゃんと話してるのに、噛み合わない理由 — 対話には“見えない設計”がある

- 感情に流される人と、感情を「材料」にする人の違い

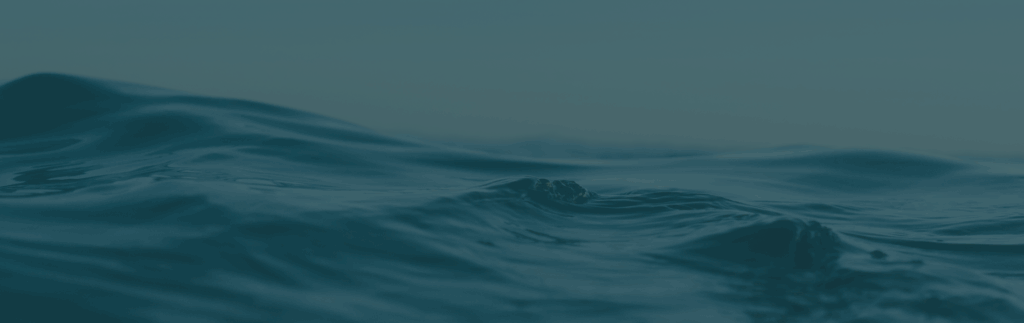
まずは、無料カウンセリングにお越しください。
所要時間:30分(Zoom)事前ヒアリングなし
話したいことがあるだけでOK。
無理な営業・勧誘はありません。あなたの「今」を聞かせてください。