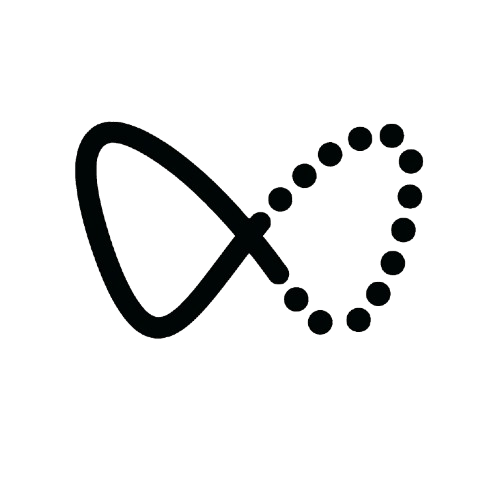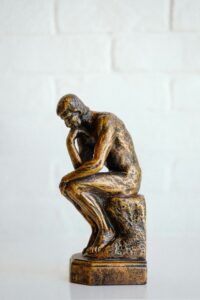「決められない」には理由がある — 意思決定を止める5つの構造要因と再設計

「決められない自分」が嫌になったことはありませんか?
選択肢の前でフリーズしてしまう。
考えているはずなのに、なぜか決められない。
——そんなとき、自己否定に陥る前に知っておきたいことがあります。
意思決定が止まるのは「性格」や「気合不足」ではなく、構造的な要因によって起こっていることが多いのです。
本記事では、行動心理学や意思決定理論の知見も交えながら、
「決められない状態」を引き起こす5つの構造的要因と、それを再設計する具体的ステップを解説します。
1. 選択肢が多すぎる(過剰選択)
心理学者バリー・シュワルツは著書『選択のパラドクス』で、選択肢の多さが満足度を下げることを明らかにしました。
選べる幅が広がるほど「他のほうがよかったかも」と後悔の余地が増え、決断へのハードルも高くなります。
再設計のヒント:
選択肢を3つ以内に絞る。あるいは「絶対に選ばない」条件から先に決めておくと判断がしやすくなります。
2. 評価軸が未定義(判断基準が曖昧)
「どっちがいいんだろう」と悩むとき、何をもって“いい”とするかが明確でないことが多くあります。
たとえば、「価格」なのか「将来性」なのか「楽しさ」なのか。
基準が曖昧なままだと、どの選択肢にも決め手がなくなってしまいます。
再設計のヒント:
先に「自分にとって重要な判断軸」を3つ書き出す。そのうえで、各選択肢を点数評価してみましょう。
3. 他者の視線を過剰に意識している
意思決定ができない背景には、「これを選んだらどう思われるか?」という他人の評価軸の内面化が潜んでいることがあります。
これは特に、社会的評価や正解を重視して生きてきた人に多く見られる傾向です。
再設計のヒント:
「○○さんならどう思うか?」という問いの代わりに「本当に自分が喜ぶのはどれか?」と問い直してみてください。
4. 失敗を避ける回路が強い(損失回避バイアス)
行動経済学の研究では、人間は得をする喜びよりも、損をする痛みを2倍以上強く感じるとされています。
このため、「間違えたくない」「失敗したらどうしよう」という気持ちが、自然と決断をブレーキしてしまうのです。
再設計のヒント:
どんな選択でも多少のリスクはある。ならば、どの選択なら「後悔の質」がマシかで考えてみると、決めやすくなります。
5. そもそも疲れている(認知資源の枯渇)
人は一日に3万回以上の意思決定をしていると言われます。
つまり、「決められない」は、脳が疲れているというサインでもあるのです。
実際、判断は朝のほうがスムーズに進むという研究結果もあります。
再設計のヒント:
「休んでから考える」「翌朝に決める」こと自体を戦略に組み込んでみてください。
意思決定は、鍛えられる
「決められない」状態は、自分を責める材料ではなく、設計ミスに気づくチャンスです。
認知の癖、選択の構造、価値基準の明確さ。
こうした要素を少しずつ整えていくことで、意思決定力は確実に育ちます。
自分の中に眠る「決める力」を信じて、少しずつ、構造を整えてみてください。
関連サービスのご案内
もしあなたが、「決めたいのに動けない」状態を抜け出したいと感じているなら、
思考の構造を整える伴走サービス mypm がお役に立てるかもしれません。
無料相談はこちらから:
https://timerex.net/s/kusegenotomato_0b3a/e36f61df
- 心の知性DQとEQを徹底解剖 — 品位が人と組織を根底から変える理由

- 知性は心にも宿る — DQとEQがチームと組織に与える本当の影響

- “従順”と“協調性”は違う — 自立したチームをつくる思考と対話のスキル

- ちゃんと話してるのに、噛み合わない理由 — 対話には“見えない設計”がある

- 感情に流される人と、感情を「材料」にする人の違い

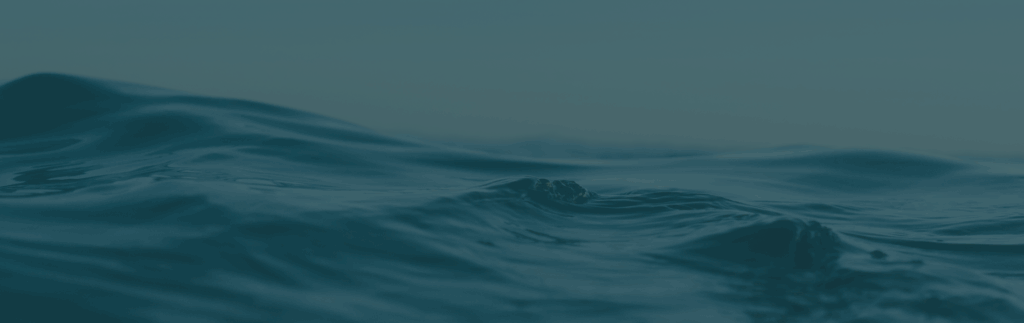
まずは、無料カウンセリングにお越しください。
所要時間:30分(Zoom)事前ヒアリングなし
話したいことがあるだけでOK。
無理な営業・勧誘はありません。あなたの「今」を聞かせてください。